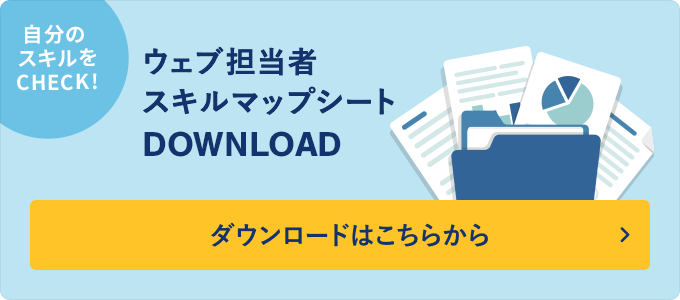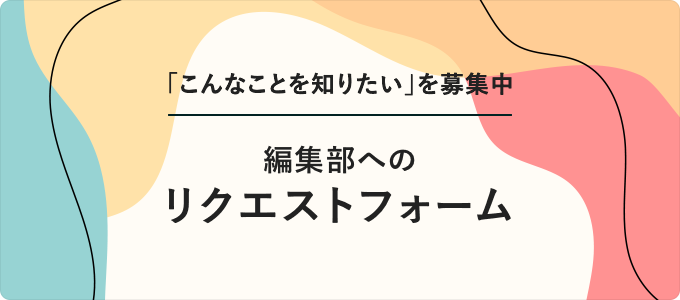Web担当者なら知っておきたい、ユーザビリティとは?
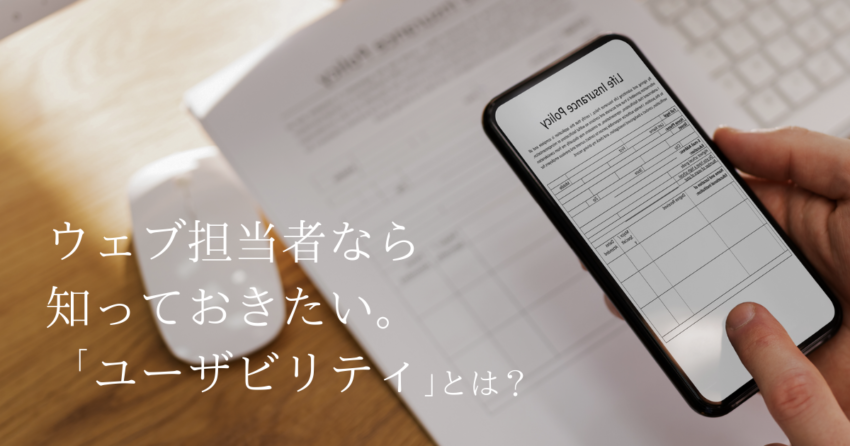
Webサイトにかかわる仕事をしていると、ユーザビリティという言葉を目にします。この記事を読んでくださっているあなたも、何度となく見たり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか。 今回は、ユーザビリティとは何かを、今一度確認してみましょう。
ユーザビリティについて、理解できていますか?
「ユーザビリティ」という概念、一般的には「使いやすさ」と理解されています。「このサイトのユーザビリティが良い/悪い」という話になることがありますが、このような場合は得てして、発言者の個人的な感覚で、使いやすいかどうかが論じられています。
「ユーザビリティが良い」「ユーザビリティが悪い」というモノサシは人によって異なるものですので、このような議論を建設的におこなうためには注意しましょう。
ユーザビリティの定義
ISO 9241-11では、ユーザビリティについて、『ある製品が、指定された利用者によって、指定された利用の状況下で、指定された目的を達成するために用いられる際の、有効さ、効率および利用者の満足度の度合い』のように定義されています。
冒頭で「製品」とあるとおり、Webに限らず製品(product)という枠組みで定義されたものですが、Webユーザビリティとして考えても十分に受け入れられる定義といえます。
さらに掘り下げて、「Webユーザビリティ」という視点で考えると、以下の3つの視点で使いやすさを向上させるための配慮が必要になります。
- 操作性
利用者が、指定された目標を達成するためにWebサイトを操作するうえでの正確さおよび完全さ - 認知性
利用者が、情報を取得し理解するうえでの認知のしやすさ - 快適性
利用者が、不快さがなくWebサイトにアクセスし、利用できること
大切なのは「特定の」ユーザーと「特定の」ゴール
ユーザビリティとは、ただ使いやすければいいという、表面的なものではありません。
上記の ISO9241-11 の定義にもあるように、「特定のユーザー」が「特定のゴール」にたどりつけることが重要です。
Webサイトの開発においては、ターゲットとなるユーザー像を明確にし、そのターゲットユーザーの行動を正しく想定すること、ユーザー行動を妨げずにできるだけスムーズにゴールにたどりつけるように設計することが大切になります。
この記事の冒頭で、「個人的な感覚」でユーザビリティを論じる人の話をしましたが、その方自身がターゲットユーザーでなければ、不毛な議論になってしまうおそれがあるというわけです。
ユーザビリティの向上は売り上げアップにもつながる
「ユーザビリティ」は大学サイトや病院サイト、自治体サイトといった公共性が高いサイトにおいて重視されますが、一般企業のサイトにおいてもないがしろにすべきことではありません。
数多くのサイト構築を支援させていただくなかで、「ユーザビリティは後回しにして見栄えを優先する」といった意見を述べる担当者のかたにもよく出会いました。
しかし、ユーザビリティを損なってまで実現する見栄えは、目立ちはしても成果には結びつかないケースがほとんどです。
利用者のことを思い、ユーザビリティに配慮したWebサイト設計や運用が、最終的には顧客の満足につながり、問い合わせや受注といった成果に結びつきます。
ユーザビリティ改善のための手法
Webユーザビリティを改善するための、おもな手法としては以下のようなものがあります。
| ヒューリスティック評価 | 専門家が経験や実績をもとにサイト構造や画面構成、デザインの分析を実施。 ユーザー行動をシミュレーションして、サイトの使いやすさ、情報探索のしやすさを分析することでユーザビリティ面の改善点を洗い出す手法。 |
| ユーザビリティテスト | サイト閲覧者に、実際に評価対象のサイトを使ってもらい、その様子を観察することで、迷ってしまう場所やエラーが起こりやすい部分などWebサイトの問題点を発見する手法。 |
| アイトラッキング | Webサイト閲覧時のユーザーの目線の動きを追跡する手法。 |
| ペーパープロトタイピング | 実際にデザインをしたりプログラミングを組んだりする前に、紙などを使った二次元の試作品(ワイヤーフレーム)で、ユーザビリティテストを実施する手法。 |
| ペルソナ作成 | あいまいな顧客像を見える化することで、ユーザー行動やニーズを具体化。ターゲットユーザーの行動特性に合わせたWebライティングや導線設計を実現する手法。 |
「ペルソナ作成」については、コラム「ペルソナとは?マーケティングに活用するための作り方とコツ」で詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。

- 株式会社あやとり
マーケティング部 - 鈴木 英美
この記事の監修者
ウェブマネジメント・アカデミー立ち上げメンバーの一人です。コンテンツ作成やメルマガ関係、インサイドセールス分野に携わりながら、このサイトのウェブ担当者として、幅広く勉強しています。
 この記事を読んだ方におすすめ
この記事を読んだ方におすすめ
-
 2024.04.17事業パートナー募集フォームを作ろう ~新たなパートナーとの出会い~いつの時代においても、ビジネスを拡大することは容易ではありません。しかし、自社に足りないノウハウや経験、リソースを補…
2024.04.17事業パートナー募集フォームを作ろう ~新たなパートナーとの出会い~いつの時代においても、ビジネスを拡大することは容易ではありません。しかし、自社に足りないノウハウや経験、リソースを補… -
 2024.03.19Webデザインを1ランクアップさせるコツいろいろな立場の方が携わっている Webサイト運営ですが、デザインのディレクションに関する部分は難しいと感じている方…
2024.03.19Webデザインを1ランクアップさせるコツいろいろな立場の方が携わっている Webサイト運営ですが、デザインのディレクションに関する部分は難しいと感じている方… -
 2024.02.06Webサイト運営に必要なスキルとは?~7つの視点から、質の高いWebサイトを作り上げるコツを学ぶ~Webサイト運営に必要なスキルを考えるときに、どんな業務があるかを知識として把握しただけでは、成果がでるサイト運営に…
2024.02.06Webサイト運営に必要なスキルとは?~7つの視点から、質の高いWebサイトを作り上げるコツを学ぶ~Webサイト運営に必要なスキルを考えるときに、どんな業務があるかを知識として把握しただけでは、成果がでるサイト運営に… -
 2023.12.20要件定義と要求定義の違いをご存じですか?サイトリニューアルに着手する前に重要な3ステップをわかりやすく解説します「こんなWebサイトにしたい」という事業主としての要求事項のなかから、外部に依頼することをまとめたRFP(提案依頼書…
2023.12.20要件定義と要求定義の違いをご存じですか?サイトリニューアルに着手する前に重要な3ステップをわかりやすく解説します「こんなWebサイトにしたい」という事業主としての要求事項のなかから、外部に依頼することをまとめたRFP(提案依頼書… -
 2023.12.04Webサイトのターゲットの決め方~ターゲット設定が重要な理由と設定方法とは?~多くの組織で起こりがちな課題に、ペルソナが定まりきれていない、事業部門によってターゲットが少しずつ異なっている、とい…
2023.12.04Webサイトのターゲットの決め方~ターゲット設定が重要な理由と設定方法とは?~多くの組織で起こりがちな課題に、ペルソナが定まりきれていない、事業部門によってターゲットが少しずつ異なっている、とい… -
 2023.11.02【図解あり】UXとはなにか?UIとの関係もわかりやすく解説「UX」というワードをよく耳にするようになりました。しかし、「UX」が何か理解されているかと言えば、まだまだ言葉だけ…
2023.11.02【図解あり】UXとはなにか?UIとの関係もわかりやすく解説「UX」というワードをよく耳にするようになりました。しかし、「UX」が何か理解されているかと言えば、まだまだ言葉だけ…